結論:この入門は「戦わない」を前提にした柔術。
距離を作る・呼吸で落ち着く・安全に立ち上がる——この3つをやさしいソロムーブで身につけ、心身の“整い(癒し)”も一緒に育てます。
安全メモ(最重要)
・本記事は非コンタクト/スパーなしが前提。
・痛み・めまい・しびれが出たら即中止。持病や既往がある方は医療者に相談。
・関節技・絞め技・投げは行いません(目的は安全な退出とセルフケア)。
・本記事は非コンタクト/スパーなしが前提。
・痛み・めまい・しびれが出たら即中止。持病や既往がある方は医療者に相談。
・関節技・絞め技・投げは行いません(目的は安全な退出とセルフケア)。
護身×癒しの原則(5つだけ)
- 観察:相手・出口・障害物を一瞬で確認(目線は柔らかく)。
- 距離:正面密着を避け45°半身+腕1本分をキープ。
- 呼吸:鼻4・口6でお腹360°に空気——心拍を落とす。
- フレーム:前腕と膝で“やさしい壁”を作り、押す>引くで距離を回復。
- 退出:安全最優先。言葉→離脱→助けを呼ぶ。勝負はしない。
まずはここから:10分ルーティン(道具いらず)
- 呼吸2分:鼻4・口6×6(肩は下げ、吐く時にお腹を軽く凹ませる)
- 骨盤コロコロ1分:仰向けで骨盤を左右に小さく揺らす
- ブリッジ2分:踵で床を押しお尻を軽く持ち上げる×8、休憩、もう1セット
- シュリンプ3分:仰向け→横向き→お尻を後ろへ“引く”動き×片側6回ずつ
- テクニカルスタンドアップ2分:片手片足で支え後退→安全に立つ×5回(ゆっくり)
※カーペット/ヨガマット推奨。痛みが出たら可動域を小さくor中止。
やさしい柔術ムーブ(ソロ版の分解)
1) ブリッジ(小)
- 目的:床反力の感覚/腰背部の連動づくり
- やり方:仰向けで膝を立て、踵で床を押す→お尻を5〜10cmだけアップ
- NG:首で反る/反動で跳ねる
2) シュリンプ(ヒップエスケープ)
- 目的:圧からの“横逃げ”を体に覚えさせる
- やり方:横向きで膝を胸に寄せ→足で床を押しながらお尻を後方へスライド
- コツ:上側の肘膝を近づけ“フレーム”を作る
3) テクニカルスタンドアップ(安全な立ち上がり)
- 目的:距離を作りながら立つ/転倒回避
- やり方:片手と反対側の足で支える→お尻を浮かせて一歩後ろへ→視線を上げて立つ
- NG:相手に背中を向けたまま前屈みで立つ
ペア練をするなら(任意)
クッションを“相手”に見立ててフレーム→シュリンプ→立ち上がりの流れをゆっくり通す。
コン タクトは最小限・会話しながら。関節・首に圧をかける操作は行わない。
クッションを“相手”に見立ててフレーム→シュリンプ→立ち上がりの流れをゆっくり通す。
コン タクトは最小限・会話しながら。関節・首に圧をかける操作は行わない。
デエスカレーション(言葉と姿勢で守る)
- 姿勢:45°半身/手のひらを見せるオープンハンド/視線は柔らかく短く
- 声:低め・ゆっくり・短文。「今は距離をとります」「落ち着いて話します」
- 言い換え:「ダメ」→「この方法が安全です」/「やめて」→「手を離してください」
- 退出:安全な出口→人のいる場所へ→通報・支援要請
※各地域の正当防衛・緊急避難の要件は法制度で異なります。過剰反応を避け、まずは離脱と通報を。
メンタルケア:その場で整える2分
- 箱呼吸:吸う4・止める4・吐く4・止める4×4周
- グラウンディング:5-4-3-2-1(見える/触れる/聞こえる/嗅げる/味)で“今ここ”に戻る
4週間プラン(週2〜3/各20〜40分)
| 週 | 目標 | メニュー例 |
|---|---|---|
| 1 | 呼吸と体幹の土台 | 呼吸→ブリッジ→骨盤コロコロ→整え |
| 2 | 横への逃げ(距離回復) | フレーム作り→シュリンプ→整え |
| 3 | 安全な立ち上がり | シュリンプ→テクニカルスタンドアップ→整え |
| 4 | 流れの統合+デエスカレーション | 呼吸→フレーム→シュリンプ→立ち上がり→言葉の練習 |
日記に「睡眠/ストレス/完了ムーブ」を1行メモ。Never miss twice(休んでも翌回戻る)。
介護・医療・教育現場向けメモ
- まず環境介入(明るさ・音・動線・人数)でリスクを下げる。
- 接触はフレーム(骨で支える)まで。痛み・ねじりは使わない。
- 合図は低くゆっくり・短文。「今から〇〇します」「1・2・3で動きます」。
- チーム合意の退出合図・連絡手順をポスター化して可視化。
Q&A
- Q. 関節技は覚えなくていい?
A. この入門では不要。目的は距離を作って離脱+心身の安定。 - Q. 体が硬いです。
A. 可動域は小さくOK。痛み0〜10で3以下を基準に。 - Q. 家族にも教えたい。
A. 10分ルーティンと“言い方”だけ共有を。危険な練習はしないこと。
今日の2分アクション
- 鼻4・口6の呼吸×6
- テクニカルスタンドアップをゆっくり2回
免責:本記事は経験と一般的知見に基づく情報であり、医療・法的助言の代替ではありません。各自の責任で安全に配慮して実施してください。

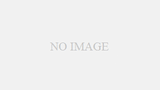
コメント