結論:受け身=「勝つ技」ではなく、頭部を守り、衝撃を分散し、骨折を避けるための転倒ダメージ最小化スキル。
高齢者ケアでは、①頭を打たない ②手首を折らない ③素早く安全姿勢に戻るが最優先です。
安全に関する重要な注意
・硬い床や狭所での練習は禁止。必ずマット/布団/カーペットで。
・痛み・めまい・心疾患・骨粗しょう症の既往がある方は、主治医・指導者の許可を得て実施。
・「手のひらで強く床を叩く受け身」は硬い床では逆効果。前腕・上腕・背面の広い面で分散が基本。
・硬い床や狭所での練習は禁止。必ずマット/布団/カーペットで。
・痛み・めまい・心疾患・骨粗しょう症の既往がある方は、主治医・指導者の許可を得て実施。
・「手のひらで強く床を叩く受け身」は硬い床では逆効果。前腕・上腕・背面の広い面で分散が基本。
この記事でわかること
- 受け身の3原則(頭部保護/丸く/分散)
- 段階別の安全練習メニュー(床→マット→椅子)
- 後ろ/横方向の受け身のコツ(前方は原則“横へ逃がす”)
- 介護士向け声かけテンプレと見守りポイント
- よくあるNGと修正、5〜10分の週間プラン
受け身の3原則(介護版)
- 顎を引く:後頭部=最優先で守る。視線はおへそ。
- 丸く落ちる:背中を少し丸め、一直線でドンと落ちない。
- 広い面で分散:背面+前腕/上腕で“面”を作り、手のひらだけで受けない。
+α:吐きながら受ける(息を止めると固まり衝撃増)/肩の力を抜く
準備(2分)
- 厚めのマット or 布団/クッション2個/低い椅子(座面40cm前後)
- 周囲1.5mの障害物撤去、靴下は滑るので裸足か滑り止め
- 見守り者は斜め後方に立ち、声かけと補助に徹する
段階練習(安全優先のプロトコル)
Step 0:呼吸と顎引き(30〜60秒)
- 仰向けで膝を立て、顎を軽く引いて首の後ろを長く保つ
- 鼻から吸い、吐きながらお腹をやわらかく凹ませる × 3回
Step 1:後ろ受け身の“形”(床ゴロ練習)
- 仰向けで膝を抱え、左右へ小さくゴロゴロ(背面の丸みを覚える)×左右各5回
- 腕は体側で“ハの字”。手のひらで叩かず、前腕〜上腕の面を軽くタッチ
Step 2:座位→ゆっくり後方着地(後ろ受け身)
- マット中央で体育座り→顎を引く→骨盤→腰→背中→肩の順で丸く着地
- 両前腕を斜め後ろへ広げ、同時に“面”でタッチ(手首は反らさない)
- 吐きながら実施 × 3〜5回/めまいが出たら中止
Step 3:横方向の受け身(側方転倒想定)
- 座位で倒れる側の脚を少し伸ばし、同側の前腕+体側で着地 → 反対手で頭部を保護
- 肩をすくめず、肩〜肘〜前腕にかけて面で受ける × 左右3回ずつ
Step 4:低い椅子からの安全“尻着き”(実用)
- 椅子の前で半歩下がる→お尻から着地→Step2の後ろ受け身へ
- 立ち上がりは横向き→四つ這い→片膝立ち→立位(呼吸を整えてゆっくり)
前方の転倒について:
手のひらで床を突かない(手首骨折リスク)。
片足を一歩前に出して横へ逃がすか、前腕全体で受けて胸を守りながら側方へ転がす。
手のひらで床を突かない(手首骨折リスク)。
片足を一歩前に出して横へ逃がすか、前腕全体で受けて胸を守りながら側方へ転がす。
介護士の“見守り&声かけ”テンプレ
- 予告:「今からゆっくり座って、丸く後ろに行きます。私が声をかけます。」
- 合図:顎を引いて—息を吐きながら—丸く
- 修正:「手のひらで叩かず、ひじ〜腕の面で」/「肩の力ストンと下げて」
- 中止基準:痛み・めまい・強い不安が出たら即中止→休憩/医療者へ相談
よくあるNGと直し方
- 後頭部を打つ:顎引き→視線おへそ→背中を丸く→腕で面を足す
- 手のひらで叩く:前腕/上腕に切替。手首の反りを作らない
- 反り腰のまま落ちる:Step1を増やし、背中の丸みを先に学習
- 息を止める:「吐きながら」を合図に固定
5〜10分メニュー(週3〜5回)
- 5分:Step0→Step1(左右各5)→Step2×3→深呼吸
- 10分:上記+Step3(左右各3)+Step4×2→起き上がり練習
起き上がりの型(実用)
- 横向き→四つ這い
- 片膝立ち(椅子や壁に手)
- 前脚で立ち上がる(吐きながら)
現場での“転倒しかけた時”の合言葉
顎引く → 丸く → 横へ逃がす → 前腕で面
(任意)動画を入れる場合
YouTubeのwatch URLを1行貼ると自動埋め込みされます。見られない環境向けにテキストリンクも併記を。
まとめ:今日の2分
- 仰向けで顎引き+吐く呼吸×3
- 座位から丸く後ろへ×1回(痛みゼロで)
※本記事は一般的ガイドです。個々の疾患・骨密度・可動域に応じて指導を受けてください。

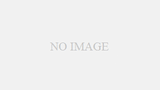
コメント