結論:柔道と介護は「体の原理」が同じ。崩し(重心コントロール)・作り(姿勢と位置)・掛け(最小の力で動かす)を、安全と尊厳のために使うのが介護版だよ。
前提(超大事):
・介護の目的は安全・自立支援・尊厳。投げ・極め・痛みを伴う操作は行わない。
・「持ち上げる/ねじる」は避け、滑らせる・押す・小分けへ。補助具とチームで無理しない。
・介護の目的は安全・自立支援・尊厳。投げ・極め・痛みを伴う操作は行わない。
・「持ち上げる/ねじる」は避け、滑らせる・押す・小分けへ。補助具とチームで無理しない。
対応表:柔道の原理 → 介護の動き
| 柔道の考え | 介護での言い換え | 現場での使いどころ |
|---|---|---|
| 崩し(相手の重心をずらす) | ご本人の前重心/足底接地をつくる合図 | 端座位→立位で「鼻をつま先より前」→立ち上がりが軽くなる |
| 作り(自分の姿勢と間合い) | 45°半身+肩幅+半歩、股関節ヒンジ | 移乗で正面密着を避ける→腰が守れる/回旋が小さくなる |
| 掛け(最小の力で技をかける) | 押す>引く/滑らせる>持ち上げる | 上方移動や体位変換は摩擦軽減で“ずらす”が基本 |
| 体捌き(回転・入り身) | 小さく回る/半歩ずつ向きを変える | 立位で車いすに向ける時、ねじらないで半円移動 |
| 姿勢(自然体) | お腹360°の腹圧+背中フラット | 前屈みの丸腰をなくす→持続作業がラク |
| 間合い | 距離・角度・声の速さを整える | 認知症ケアで“前じゃなく隣”に立つ→安心と同意が得やすい |
| 受け身 | 職員の転倒リスク対策 | 床・段差・動線を整備/職員研修で安全な倒れ方を学ぶ(利用者には適用しない) |
ケース別:こう変えると楽になる
1) ベッド端座位→立位→車いす
- 崩し:足底全面接地→「鼻をつま先より前」合図で前重心。
- 作り:介助者は45°半身+股関節ヒンジ、胸は長く。
- 掛け:押して一緒に立つ→小さく半円で向きを合わせ、座面を目で確認してゆっくり。
NG:抱え上げ/正面から密着/腕だけで引く。
2) ベッド上の上方移動
- ご本人は膝立て。介助者は腹圧→ヒンジ。
- 肩と骨盤を同じ方向へ滑らせる(持ち上げない)。
- 「1・2・3」でかかとで押してもらう=共同作業。
3) 体位変換(仰臥→側臥)
- 倒す側の足を上にして、肩と骨盤を同時に“転がす”。
- 介助者は45°半身、押す>引くで最小の力。
5つの原則(覚えやすい版)
- 腹圧:鼻4・口6でお腹360°を軽く張る(会話できる強度)。
- ヒンジ:腰で曲げない。お尻を後ろへ、背中フラット。
- 45°半身:正面で詰めない。回旋は小さく。
- 押す・滑らせる:引っ張らない・持ち上げない・小分けにする。
- 合図:短文で予告→同意→「いきます、1・2・3」。
60秒でできる“職員ミニドリル”
- ヒンジ10回(棒 or 壁で背中フラット確認)
- 45°半身→半円回り(空間で向きを変える練習)
- 声かけリハ:「鼻をつま先より前」「今から立ちます」をゆっくり言う
※利用者さん相手に新操作を試さない。まず職員同士で。
よくある質問
- Q. 柔道を現場で使っていいの? 技は使わない。原理(姿勢・重心・体捌き)だけを安全介助に転用。
- Q. 腰がすぐ張る… ヒンジ不足と正面密着が原因のことが多い。45°半身+押す・滑らせるへ。
- Q. 認知症で立てない時 焦らず予告→待つ→環境調整。高さ・足底・視線・音/光を整えてから再トライ。
今日の2分アクション
- 鏡で自分のヒンジを10回チェック(背中フラット)。
- 「鼻をつま先より前」「45°半身」を声に出す合図で練習。
- 明日の移乗で押す>引くを1回だけ意識して使う。
本記事は現場経験と一般的知見に基づくガイドです。個別ケースはPT/OT/看護・医師と連携して判断してください。

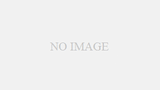
コメント